
最新ニュース
2024年4月24日
2024年4月24日
2024年4月24日
2024年4月23日
2024年4月23日
2024年4月23日
フォトニュース
釣り情報
2024年4月18日
2024年4月11日
2024年4月4日
ショッピング情報
アート工房紀の国 28日~5月7日まで開催 15周年記念セール
2024年4月24日
英語専門塾 Be 弱点を強化! 一人ひとりに合った指導を
2024年4月22日
トータルファッション クスオカ 24日から29日まで 初夏物コレクション
2024年4月22日
お知らせ
2024年3月19日
2024年3月12日
2024年1月13日
本のひだかや
嵐が丘 エミリー・ブロンテ著New!!
2024年4月18日
不疑 葉室麟著New!!
2024年4月18日
脱マウス 最速仕事術 森新著New!!
2024年4月18日
安閑園の食卓 辛永清著New!!
2024年4月18日









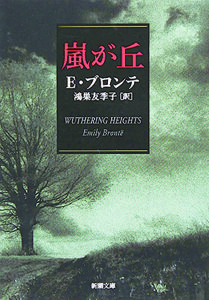
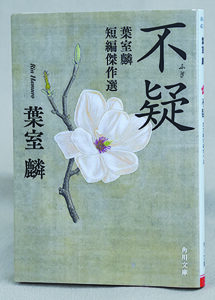
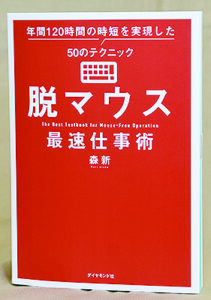
-204x300.jpg)