
最新ニュース
2024年4月26日
2024年4月26日
2024年4月26日
2024年4月25日
2024年4月25日
2024年4月24日
フォトニュース
釣り情報
2024年4月25日
2024年4月18日
2024年4月11日
ショッピング情報
アート工房紀の国 28日~5月7日まで開催 15周年記念セール
2024年4月24日
英語専門塾 Be 弱点を強化! 一人ひとりに合った指導を
2024年4月22日
トータルファッション クスオカ 24日から29日まで 初夏物コレクション
2024年4月22日
お知らせ
2024年3月19日
2024年3月12日
2024年1月13日









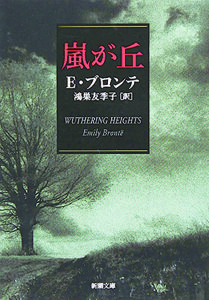
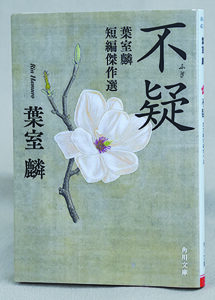
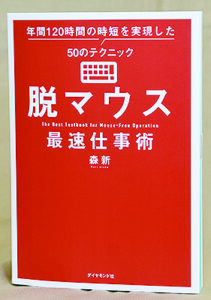
-204x300.jpg)