
最新ニュース
2024年4月20日
2024年4月20日
2024年4月20日
2024年4月19日
2024年4月19日
2024年4月19日
フォトニュース
釣り情報
2024年4月18日
2024年4月11日
2024年4月4日
ショッピング情報
cotton(コットン) 春のお出かけに♪
2024年4月17日
かわべテニス公園 5月26日までの期間限定 春の行楽弁当♪
2024年4月17日
あさの屋 人気メニューがリニューアル! エビクリームコロッケ
2024年4月15日
陶器のマスヤ 世界に一つだけの 母の日の贈り物♥
2024年4月10日
お知らせ
2024年3月19日
2024年3月12日
2024年1月13日
本のひだかや
嵐が丘 エミリー・ブロンテ著New!!
2024年4月18日
不疑 葉室麟著New!!
2024年4月18日
脱マウス 最速仕事術 森新著New!!
2024年4月18日
安閑園の食卓 辛永清著New!!
2024年4月18日









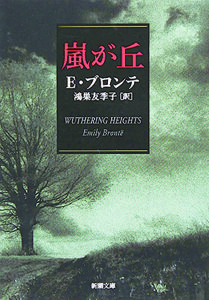
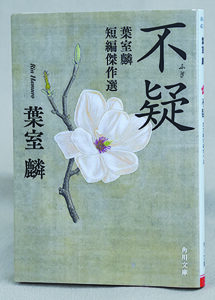
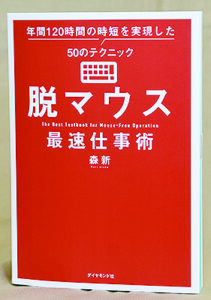
-204x300.jpg)